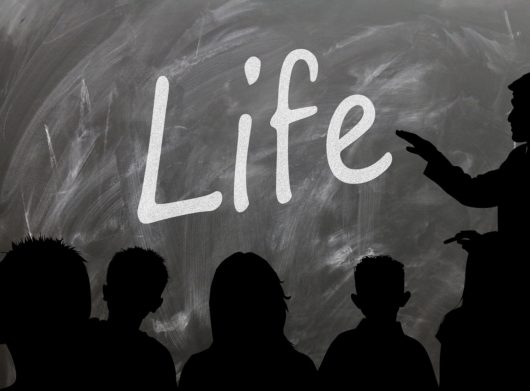
私の夫は、宮城県の中学校の英語の教師でした。
2008年2月7日、いつものように仕事に出かけた夫が、帰ってくることはありませんでした。
授業中に乱入してきた別のクラスの生徒をなだめ、廊下にでて指導をした後に3階の廊下の窓から飛び降りてしまいました。
夫43歳のときでした。二人の子どもは、まだ6歳と4歳の可愛い盛りでした。

今年で17回忌になります。
夫は、担当教科の英語の楽しさを伝えたい、部活においては得意のバレーを思いっきり教えたいと、生徒と真正面から向き合い、体当たりで取り組んでいました。
いつも、そんな思いを熱く語っていた夫。
私は、そんな夫がとても頼もしく、誇りでした。

しかし、被災した学校に転勤してから、状況が変わりました。
帰宅時間が遅い毎日。帰宅してからも遅くまで、パソコンに向かう日々。
土日も部活で、毎週のように休みなしの出勤。

他の学校に比べて事務量が多く、本来の授業の準備ができないと言っていました。
部活においても、専門外のソフトテニス部の顧問。
そこには外部コーチがおり、活動計画はコーチと親の会で作成されていました。
技術指導はもちろん、運営に対しても意向を反映させることができず、コーチが決めたことにただ従うだけでした。
夫は、まったく生徒に指示を出したりすることが、できなかったのです。
やっとの思いで3年生を送り出した1年目。
ほっとしたのもつかの間、2年目も3年生の担任になりました。
全体的に英語の学力が低い学校だった為、英語は1年生が大事だから、1年生からしっかり指導したいという、夫の願いは叶いませんでした。

2年目の夏休み後から、毎日吐き気をもようすようになり、「学校休むかな・・・」と言うようになりました。
夫の様子から、病院を受診した方がいいと思っていた私は、何度も勧めましたが忙しくて学校休めないと言って、病院へ行くことはありませんでした。
夫の死後、医学的知見から2年目の8月頃には、うつ病を発病していました。
冬休みを過ぎると、カレンダーを見ては「卒業まであと何日・・」と毎日数えるようになりました。
夫が毎日、どんな思いで学校の門をくぐっていたのかと思うと、胸が張り裂ける思いです。
夫の死後、生きる希望を見いだせず、夫を救えなかった自責の念に苦しむばかりの日々でしたが、生前の夫の仕事の多忙さや、夫が話していたことを思い出すにつけ、これは単なる自死ではないと、考えるようになりました。
そして、教職員組合の先生に相談をし、夫の教育者としての名誉を守りたいという思いから、「公務災害認定請求」をする決意をしました。
しかし、認定までの道のりは決して簡単なものではありませんでした。
私の知らなかった、様々のことがわかりました。
夫の仕事は、想像以上に多忙で、学校がかなり荒れていたこと。
夫の給食に、生徒により、睡眠薬が入れられたこともあったこと。
黒板に「死ね」の書き込みが何度もあったこと。
亡くなる前日も「死ね」の書き込みがあり、夫は「あなたたちを卒業させるまでは死ねない」と静かに言い、黒板を消したそうです。
ひとりの生徒にいつも付きまとわれ、毎日のように授業妨害を受けていたこと。
生徒の授業妨害などの問題行動に対して、学校全体で対応するということはなく、すべて、ひとりひとりの教師の責任の上で指導が行われていました。
各学年の問題も、全体で共有することはなく、他の学年でどんな問題が起こっているのかわからない状態でした。
夫はひとりで立ち向かい、苦しんでいたのです。
この2年間は、英語の授業、生徒指導、学級経営、部活動と夫が教師として大切に積み上げてきたものが、激務の中ですべて破壊された2年間だったと思います。
公務災害認定請求をしてから2年2ケ月後に、不当にも「公務”外”の災害」と認定されました。激務に起因する死であることは間違いないのにも関わらず、不当な認定に悔しく、怒りでいっぱいでした。
その後、審査請求をして、審査会において、2013年5月「公務上の災害」と認定されました。この間4年の歳月が流れました。
夫の遺書に「俺は生きたい。ここから立ち直り、戦いたい。このまま終わりたくはない。」とありました。
志半ばで教壇に立つことができなくなった夫は、どんなに悔しかったかしれません。
公務災害が認定になり、夫の名誉は守られましたが、夫が私たちのもとに帰ってくることはありません。
今でも、夫を救えなかったことは、悔やまれてなりません。
教師の多くは、日常的に多岐にわたる業務をしています。
慢性的な多忙で、荷重な勤務の改善などを、抜本的に見直すことをお願いいたします。
夫の死を教訓として、無駄にしないでください。
すべての人たちが、健康で安心して働くことができる社会であってほしいと、願うばかりです。
宮城過労死を考える家族の会 大泉 淳子